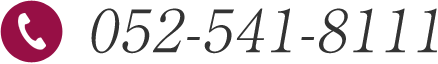財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
法律でも、離婚の際に相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)を定めています。
重要なポイントは、財産分与の対象となる財産とそうではない財産を把握することです。
きちんと把握していくことで、財産分与の話し合いがスムーズに進みます。

財産分与の種類
財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。
① 清算的財産分与
夫婦が婚姻生活により共同して築いた実質的夫婦共同財産の清算
対象となる財産
分与の対象になる財産は「結婚中に夫婦の協力によって得た財産で「共有財産」と「実質共有財産」の二つに分かれます。
「共有財産」とは、名実ともに夫婦の共有になっている財産のことをいいます。
「実質的共有財産」とは、名義は夫婦のどちらかの一方になっているが、夫婦が協力して取得した財産のことをいいます。
対象とならない財産
- 1
- 結婚前の預貯金
- 2
- 結婚前の所有物
- 3
- 親の相続で得た財産
これらは、夫婦それぞれに所有権がある「特有財産」とされます。
しかし、財産分与を請求する者が、その特有財産の減少防止に協力したのであれば、その一部について分与を認める判例もあります。
② 扶養的財産分与
離婚によって生活に困窮する他方に対する一方による扶養
例えば、長年専業主婦だった妻や夫が、高齢や病気などの理由で職に就けない場合や、幼い子供をひとりで養育しており職に就けず生活が困窮する場合などの場合、「扶養」的な意味合いで財産分与がなされることをいいます。
但し、離婚後に経済的に安定した生活ができると判断できる場合は、扶養的な意味の財産分与の義務は他方にはありません。
また、財産分与を請求される側に、一方を扶養できるだけの経済力がなくては、扶養的財産分与は認められません。
扶養的財産分与額について
扶養的財産分与の額は、次のようなことを考慮して判断されます。
- 婚姻期間
- 有責の有無
- 程度
- 年齢
- 子供の養育
- 疾病
- 身体的障害ないし精神的障害
③ 慰謝料的財産分与
有責の行為によって夫婦の婚姻生活を破綻に導いた他方に対する一方の損害賠償請求
離婚の際に、慰謝料の請求が問題になる場合が多くあります。
慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものですので両者は本来別々に算定して請求するのが原則です。
しかし、両方ともに金銭が問題になるものであるため、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払をすることがあります。
この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので「慰謝料的財産分与」と呼ばれているのです。
財産分与できる期間
財産分与を請求できるのは、離婚成立の日から2年間です。
この2年間という期間は時効の期間ではなく法律用語で「除斥期間(じょせききかん)」といわれるもので、時効の場合と異なり中断等がありませんから注意が必要です。